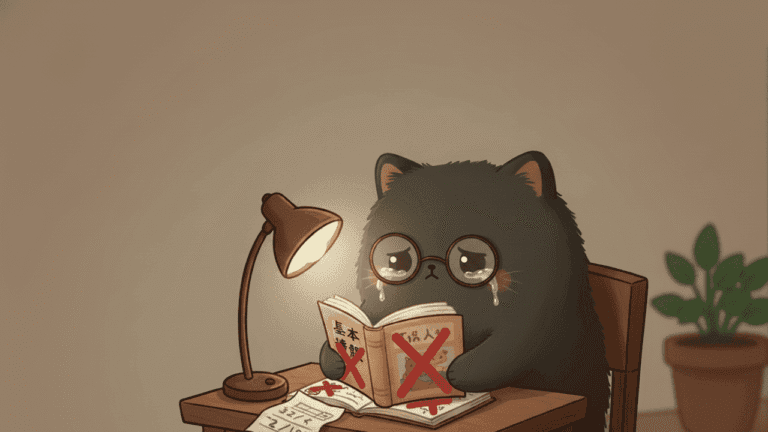「基本情報技術者試験に落ちた……」
そう感じた瞬間、悔しさや焦り、そして「自分には向いていないのでは」という不安が頭をよぎる方も多いでしょう。ですが、実はこの試験は多くの受験者が一度はつまずく難関試験です。落ちた経験は決して恥ずかしいことではなく、むしろ次の合格に向けて戦略を練り直すチャンスです。
- 基本情報に落ちた原因を明確にできる
- 次回受験のタイミングや制度を理解できる
- 落ちた後に効果的な勉強法を知れる
- 落ちた経験を活かして合格へ進む道筋が描ける
基本情報に落ちた理由と実情
- 落ちる人が多い試験という認識
- よくある落ちた原因パターン
- 落ちた回数に対する焦りと誤解
落ちる人が多い試験という認識
「基本情報技術者試験に落ちた」と聞くと、自分だけが失敗したような気持ちになるかもしれません。
しかし実際には、この試験でつまずく人は決して少数派ではありません。
基本情報技術者試験(FE)は、IT国家資格の中でも出題範囲が非常に広く、合格率は例年20〜30%前後にとどまっています。つまり、受験者のうちおよそ3人に2人は不合格という現実があります。情報処理技術者試験全体を見ても、基本情報は「最初の関門」として多くの受験者が苦戦する試験です。
このように考えると、「落ちた」という経験は珍しいことではなく、むしろ多くの人が通る過程です。自分を責めるより、「今ここからどう立て直すか」に意識を向けることが大切です。
さらに、試験制度は近年改定され、通年CBT方式によって、好きな時期に再受験できるようになりました。以前のように半年待つ必要もなく、早めの再挑戦が可能です。
この柔軟な制度は、落ちた後にすぐ行動へ移すチャンスを与えてくれます。
「落ちた=終わり」ではなく、「次に活かせる経験」として捉えることが、合格への第一歩です。
よくある落ちた原因パターン
「基本情報に落ちた」と検索する方が自分に当てはまりそうな原因として、いくつか典型的なパターンがあります。
- 午前はある程度点数を取れたが午後で伸び悩んだ。
- 学習時間や方法が曖昧で、勉強が浅かった。
- モチベーションが下がり、途中で勉強が停滞した。
- 差がつく問題(例えばアルゴリズム・プログラミング系)に取り組めていなかった。
こうした原因を振り返ることで、「次回どう学ぶか」の方向性が見えてきます。
落ちた回数に対する焦りと誤解
「基本情報 落ちた 回数」が増えると、自分には向いていないのではという焦りが出てきがちです。実際、掲示板では「3回落ちて生きてるのが恥ずかしい」という投稿も見られます。 (基本情報技術者試験ドットコム)
ただし、何度挑戦しても制度上再受験の制限はなく、回数そのものが評価に直接響くわけではありません。受験回数を必要以上に気にしてしまうのは、むしろ学習計画を立てる上でマイナスになります。
落ちた回数が多くても、原因に向き合って対策を立てていれば、次の合格への可能性は十分にあります。
基本情報に落ちた後の再受験準備方法
- 次回受験のタイミングと制度の確認
- 学習計画の見直しと効果的な対策
- 落ちた経験を武器に変えるマインドセット
次回受験のタイミングと制度の確認
「基本情報に落ちたら次いつ受けれる?」という疑問に対して、受験制度上のポイントを整理します。試験を主催する 情報処理推進機構(IPA)の情報処理技術者試験制度において、同一試験区分を再受験するには、前回の受験日から30日以上経過している必要があります。 (基本情報技術者試験ドットコム)
ただし、受験を欠席(申込済みで受験しなかった)した場合はこの制約が適用されないケースもあるようです。
さらに、試験制度の改定で通年受験(CBT方式)になったため、受験日が以前より柔軟になりました。
以上を踏まえ、「次回いつから申し込めるか」「いつ受験できそうか」のスケジュールをつくることが再受験準備の第一歩です。
学習計画の見直しと効果的な対策
「基本情報に落ちた」後は、次に合格するために学習戦略を刷新することが鍵となります。以下のステップで計画を立てましょう。
- 過去問の演習量を増やす:特に午前試験・午後試験ともに「初見で解ける問題」を増やすことが有効とされています。
- 苦手分野の特定:午後のアルゴリズムやプログラミング設問で点が伸び悩むケースが多く、重点的に取り組む必要があります。
- 学習時間・モチベーション管理:落ちた経験を活かして、「なぜ受けるか」を明確にし、習慣化できる学習ペースを作ることが推奨されます。
- 模擬試験や時間配分トレーニング:特にCBT形式では問題数・時間配分が変化しており、実践的なトレーニングが有効です。
これらを組み合わせることで「ただ落ちないように受ける」から「着実に合格に近づく」学習へ切り替えることができます。
落ちた経験を武器に変えるマインドセット
落ちたという経験そのものを前向きな要素に変えることも、再挑戦には大切です。以下のようなマインドセットが役立ちます。
- 失敗から学ぶ:何が原因で落ちたかを具体的に振り返り、その改善にフォーカスします。
- 継続的に挑戦する:回数に関係なく、「次回に向けて確実に前進する」姿勢が重要です。
- 自分を責めすぎない:掲示板などでは「恥ずかしい」と感じる投稿もありますが、落ちた経験を気にするより次回の行動に目を向ける方が建設的です。
以上を意識すれば、落ちた経験も将来の成長素材になります。
基本情報に落ちたあとの合格戦略
- 午前試験突破に向けたコツ
- 午後試験で差をつけるための対策
- 再受験後の「次いつ受けれる?」疑問への対応
- 勉強ツール・参考教材の選び方
- 継続して合格にたどり着くための習慣化
午前試験突破に向けたコツ
基本情報技術者試験の午前試験で合格するためには、まず「知識の網羅」と「スピード対応力」の両立が欠かせません。この試験では、IT全般にわたる幅広い分野から出題されるため、過去問演習を繰り返して出題傾向を体で覚えることが何より効果的です。特に、似たテーマが形式を変えて出題される傾向があるため、「問われ方」に慣れることが重要になります。
また、多くの受験者がつまずくのは、ネットワークやデータベース、セキュリティなどの基礎分野です。こうした分野を「なんとなく理解したつもり」で済ませてしまうと、試験本番で確実に差がつきます。自分の苦手領域を明確にして集中的に復習し、弱点を潰すことが得点アップの近道です。
さらに意識したいのが時間配分です。午前試験は短時間で大量の問題を処理する形式のため、どんな問題でも瞬時に判断する力が求められます。過去問を解く際には、単に正解することを目的とするのではなく、本番と同じ制限時間内でどの程度スピーディに解けるかを常に意識しましょう。こうした練習を重ねることで、「考え込まずに選択できる」反射的な判断力が身についていきます。
通勤時間やスキマ時間を活用して、スマホアプリや過去問道場を使うのもおすすめです。毎日少しずつ知識を更新し続けることで、試験本番での対応力が格段に上がります。
午後試験で差をつけるための対策
午後試験は「理解をどのように応用できるか」を問う構成になっており、ここで点数を落とす人が非常に多いのが実情です。午前試験と違い、単なる暗記では対応できません。文章を読み解き、処理の流れを理解し、答えを導く「考える力」が試されます。
まず意識すべきは、出題傾向の把握です。過去問を通して頻出分野を見極め、自分が得点源にできるテーマを決めましょう。すべてを完璧に解こうとするより、2〜3分野を確実に得点できるレベルに仕上げるほうが効率的です。また、アルゴリズムやプログラミングの問題は避けて通れません。苦手意識のある人は、動画講座や演習ドリルを活用して基礎から理解を積み上げましょう。処理の流れを頭の中でイメージしながら読む練習を繰り返すと、設問の意図をつかむ力が自然と養われます。
試験直前期には、模擬試験形式でのトレーニングが効果的です。実際の制限時間で問題を解くことで、集中力の維持や時間配分の感覚が身につきます。CBT形式の試験では、1問あたりの時間が限られているため、どの問題にどれだけ時間を使うかを意識的に調整できるようにしておくと本番で慌てません。
午後試験は、慣れと経験を積むほど得点が安定します。焦らず、少しずつ「読む力」「考える力」「書く力」を鍛えることが、確実な合格への道となります。
再受験後の「次いつ受けれる?」疑問への対応
「落ちたけれど、次はいつ受けられるの?」と不安に思う人も多いでしょう。基本情報技術者試験を実施するIPA(情報処理推進機構)では、再受験の条件を明確に定めています。前回の受験日から30日以上が経過すれば、同一区分の試験を再受験することが可能です。つまり、わずか1か月後にはもう一度挑戦できるということです。
しかも、再受験の回数に制限はなく、何度でも挑戦できます。以前のように春・秋の年2回しか受けられない時代とは違い、今は通年で実施されるCBT方式に移行しているため、全国の試験会場から自由に日程を選べます。これは「落ちた直後の勢いで再挑戦したい」という人にとって大きなメリットです。
さらに、申込済みでも受験を欠席した場合には、この30日ルールが適用されないケースもあります。つまり、スケジュール調整さえできれば、より早く再受験に臨むことも可能なのです。
こうした制度の柔軟化により、「落ちたら半年待ち」という時代は完全に終わりました。落ち込む時間を最小限にして、早めにリズムを取り戻すことが次の合格につながります。前回の試験から1か月後を目安に再挑戦の予定を立て、そこから逆算して学習スケジュールを組み立てると、無理のないペースで再スタートが切れるでしょう。
勉強ツール・参考教材の選び方
落ちた経験を活かして、教材選びも見直しましょう。おすすめのポイントは以下の通りです。
- 過去問演習サイト・アプリ:午前・午後ともに実践力を上げることができます。
- 動画講座やオンライン講座:アルゴリズムやプログラミングが苦手な人向けに分かりやすく解説されているものがあります。
- 模擬試験集や練習問題集:時間配分を体で覚えるために、初見問題に挑戦できる教材が有効です。
これらを使いこなすことで、落ちた原因を克服しやすくなります。
継続して合格にたどり着くための習慣化
基本情報技術者試験に合格する最大の鍵は、「一気に頑張ること」ではなく「続けること」です。どんなに効率的な勉強法でも、継続できなければ結果にはつながりません。逆に言えば、少しずつでも学びを積み重ねられれば、確実に合格へ近づいていきます。
まず意識したいのは、「勉強を生活の一部にする」ことです。勉強を“特別なイベント”にしてしまうと、忙しい日や気分の乗らない日に続かなくなります。通勤の電車で過去問を1問解く、寝る前に前日の復習を5分だけする――そんな小さな行動でも構いません。毎日机に向かわなくても“思考を止めない”ことが大切です。
また、間違えた問題をそのままにせず、「なぜ間違えたのか」を記録して見直す習慣をつけましょう。ノートやアプリにミスの理由をメモし、定期的に振り返るだけでも理解の定着度が大きく変わります。これは一見地味ですが、「間違いノート」は最強の教材になります。過去の失敗を整理して可視化することで、自分の弱点がクリアになり、学習の方向性がぶれません。
さらに、モチベーションを保つためには「成長を実感する仕組み」を取り入れることが効果的です。例えば、1週間ごとに「今週はアルゴリズム分野を5問解けた」「午後問題で初めて合格点を超えた」といった小さな成果を記録してみましょう。進歩を見える化することで、自己肯定感が上がり、継続のエネルギーになります。
落ちた経験を無駄にしないためには、「一度で受かる人より、諦めず続ける人の方が強い」という意識を持つことが大切です。学習習慣を積み上げることで、焦りや不安よりも「確実に成長している実感」が勝るようになります。1日10分でも構いません。今日の積み重ねが、次の合格通知につながります。焦らず、淡々と、継続を力に変えていきましょう。
基本情報に落ちてから合格へ向けたまとめ

- 落ちた経験が過去になるよう学び直しを図る
- 制度・再受験可能日の理解をもとにスケジュールを組む
- 午前試験・午後試験ともにポイントを押さえた対策を行う
- 学習ツール・教材の選定を見直す
- 毎日の習慣を作り、継続できる仕組みを整える
- 落ちた回数に囚われず「前に進む姿勢」を持つ
- 次回受験に向けて「なぜ受けるか」を明確にする
- 過去問演習を繰り返し、得意分野・苦手分野を把握する
- 模擬試験や時間配分のトレーニングを通じて実践力を高める
- プログラミング・アルゴリズム対策を重点的に行う
- 再受験申込可能日を確認し、逆算して勉強開始
- メンタルケアを忘れず、落ちた経験をネガティブにせず活かす
- 周囲の受験者数・合格率データを参考に「自分だけじゃない」と理解する
- 場合によってはスクールや講座の活用も検討する
- 落ちたからこそ見える改善点を活かして合格を手にする
以上を踏まえ、今回「基本情報に落ちた」という経験を次に活かし、新たな合格に向けて前進していきましょう。